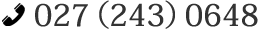★総合歯科 万代総合歯科診療所の日常臨床 噛み合わせの修正★
『くいしばり』していませんか? 定期的に噛み合わせの確認・指導・修正をしてもらっていますか?
今回提示の写真は、万代総合歯科診療所にて全体的な治療を受けてから定期検診に参加され、約6年経過した患者さんの左上奥歯です。1枚目:クラウン(人工のかぶせもの)を装着した直後
金属のクラウンが、左上の一番奥歯です。


2枚目:クラウンを装着後 約6年経過時です。


拡大して比較してみましょう
3枚目:クラウンを装着した直後の拡大写真


4枚目:クラウンを装着後 約6年経過時の拡大写真